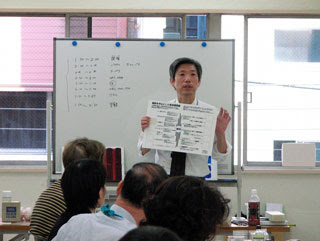今回のワークショップには17名の方にご参加いただきました。場所はホルベイン画材(株)本社ビル3階にて、メイン講師のホルベイン工業(株)技術部部長 小杉弘明より、「水彩絵具メディウム技法と基底材、画筆について」をテーマに講座を開始しました。

(今回からワークショップの様子を動画でもご覧いただけます。)
さて、日本では水彩というと紙に絵具と水だけで描くイメージが強いのですが、英国をはじめ水彩の盛んな欧米では昔からもっと自由にいろんな素材・製品や技法が使われてきました。中でも、透明性を変えたり、紙への絵具のにじみ方を調節したり、より幅広い水彩表現に役立てるための製品を総称して「水彩メディウム」と呼んでいます。こうした製品を使った技法を中心に、さまざまなテクニックもご紹介し、実習していただきました。
まずは絵具の中身の話から。
色の粉である顔料を紙に固着させるための糊(メディウム)として、水彩絵具にはアラビアゴムというアフリカ産のアカシアの木から採れる樹脂が使われています。透明水彩と不透明水彩(ガッシュ)の違いは、顔料とアラビアゴムの配合比の違いです。
ひととおり製品の説明が終わったら、今度はそれらの効果を実際に試していただきます。講師の指示する手順に従ってひとつひとつの技法を体験。絵具のはじきを抑えて滑らかににじませるオックスゴール。水彩画の白抜きが簡単にできるマスキングインク。きらきら輝くイリデッセントメディウムは、今回は歯ブラシにつけてはじく「スパッタリング」という技法で星みたいに散らせてみました。ついでに、マスキングインクをスパッタリングして星を白抜きにするウラ技までこっそり伝授。

実は、水彩画では絵具と同じぐらい紙も大切です。水彩用の他のさまざまな紙にも同じ技法で描き比べていただきました。表面の丈夫さや絵具のしみ込むスピードの違いなどで、にじみ方や発色、使える技法も違ってくるのです。

単純に見えて、奥の深い水彩画。絵具の性質や技法、紙の性質を知ることで、思い通りの画肌や発色を手に入れることができます。内容盛り沢山の3時間、みなさん熱心に取り組んでいただきありがとうございました。
5月と6月のワークショップは、いよいよ「油絵の材料に関する基礎講座」です。是非この機会をお見逃しなく。今後のワークショップについて、詳しくは「2010年度、ホルベイン【ワークショップ】開催日程が決定いたしました。」をご覧ください。